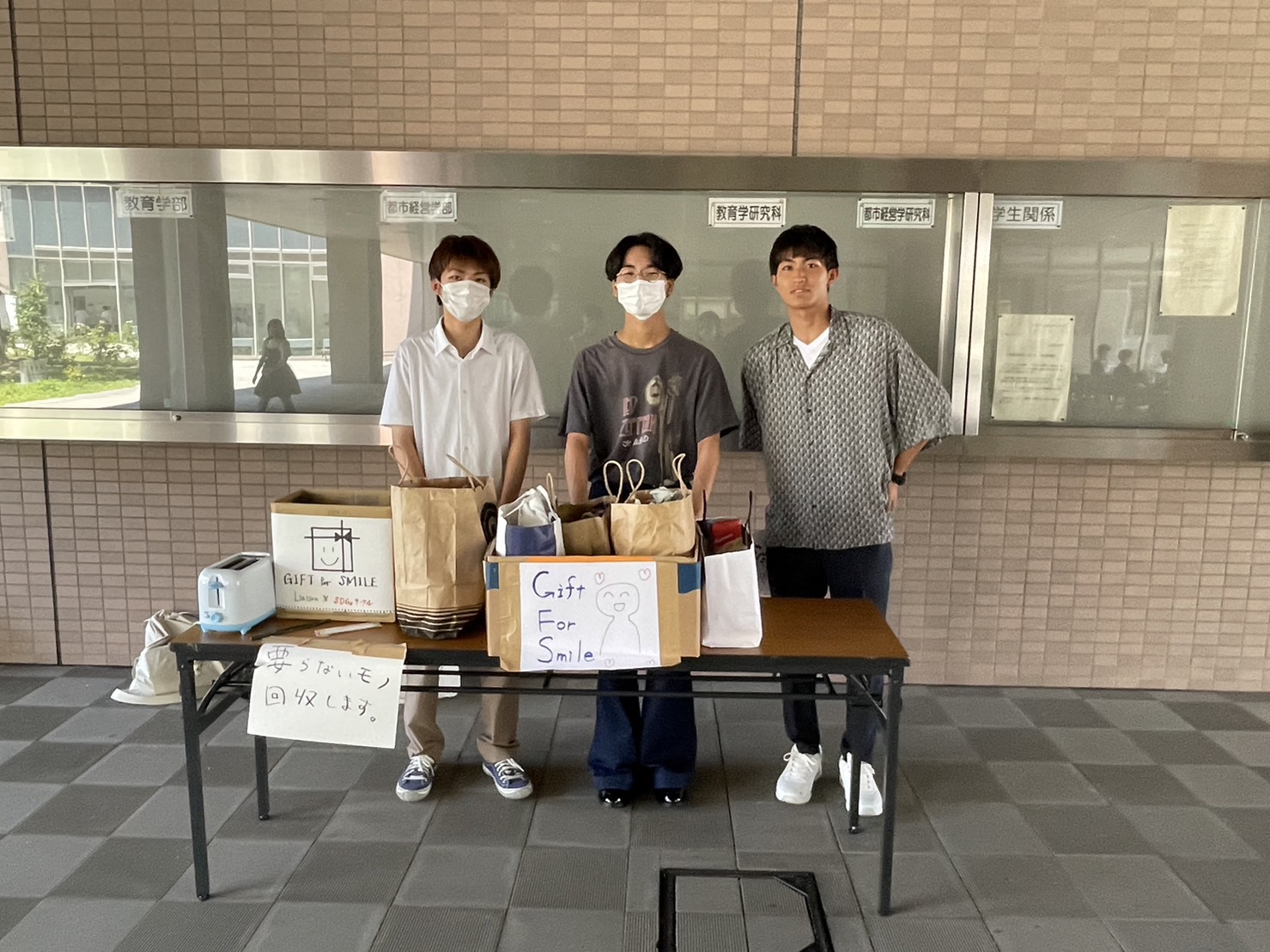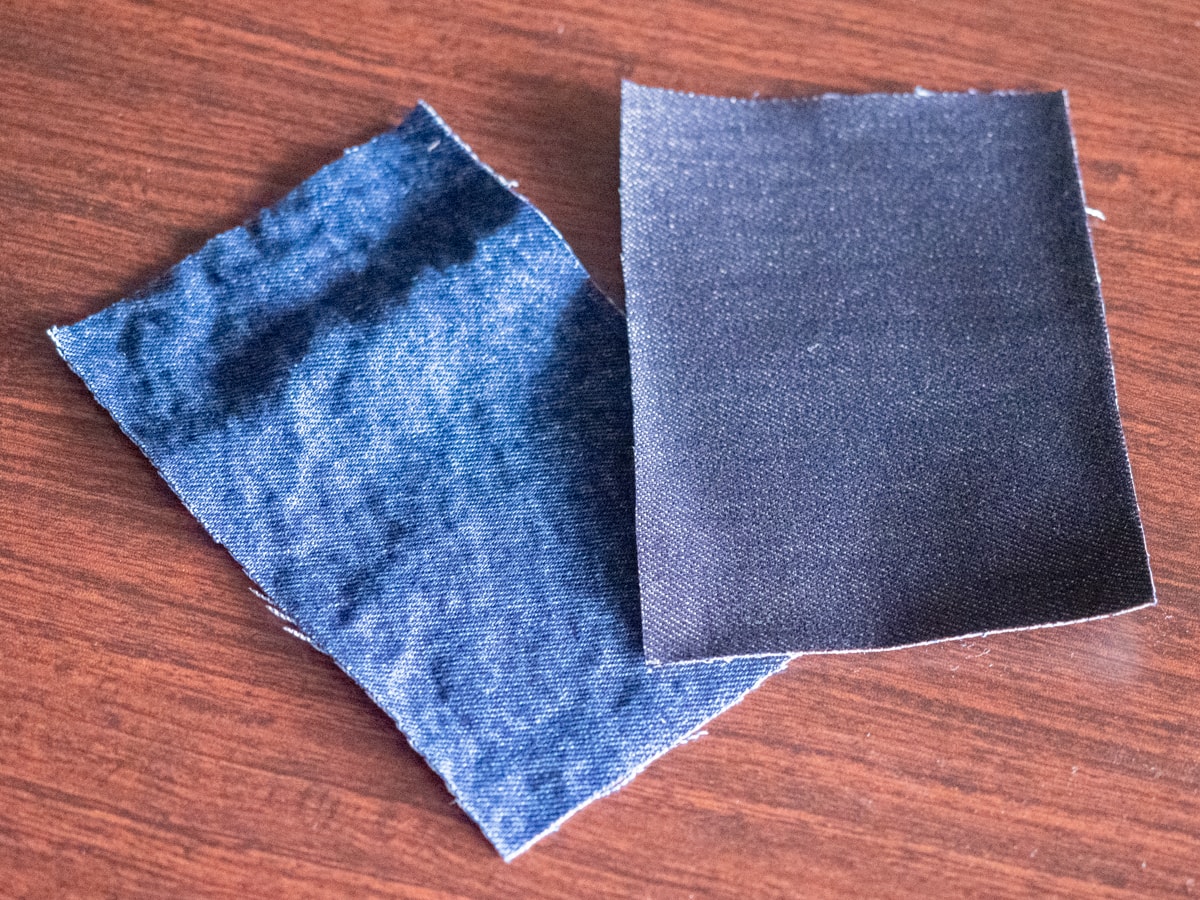SDGsプロジェクト
ストーリー
悩める若者に安心できる環境を与え、自立や就労を 支援する「どりぃむスイッチ」の活動


社会参加に困難を抱える若者を支援し、自立や就労をサポート
特定非営利活動法人 どりぃむスイッチは、社会参加に困難を抱える若者とその家族が、主体的で幸せに生きられることをめざし、若者の未来を拓くための事業に取り組んでいます。
どりぃむスイッチの現在のおもな事業は、働きたい若者のための就労支援事業「ふくやま地域若者サポートステーション」、社会的養護経験者等に対して暮らしをサポートする施設「アフターケア事業所 カモミール」、女子の自立を応援する事業「自立援助ホーム エクリュ」、地域で若者をサポートしている団体をつなぐ「ひろしま・おかやま若者サポートネットワーク」などです。

居場所づくりのきっかけは我が子の不登校
どりぃむスイッチは2012年に任意団体として始まりました。どりぃむスイッチの創立者であり、理事長である中村 友紀(なかむら ゆき)さんは、活動開始の経緯について次のように語ります。
「きっかけは我が子が不登校になったことでした。少しでも外に出られるように、不登校の子向けの居場所となるような施設がないかと探したのですが、当時の福山市周辺には見当たらなくて。その経験から、自ら不登校の子や引きこもりの人に向けたフリースペースを開設したのがどりぃむスイッチの始まりです」
フリースペースは一歩踏み出したい若者が日常的に行ける場所として開放していましたが、中村さんはIT関係の実務経験があったことから、フリースペースでITスキルを学べるようにしました。するとパソコンやITに興味がある若者が集まってくるようになり、参加者同士で教え合うようになったといいます。
やがてフリースペースでは、ボードゲームが好きな人、ホームページ制作が得意な人などが集まるように。そして、参加者がやりたいことをやるスタイルになり、参加者も10代から40代まで幅広い年齢層になりました。
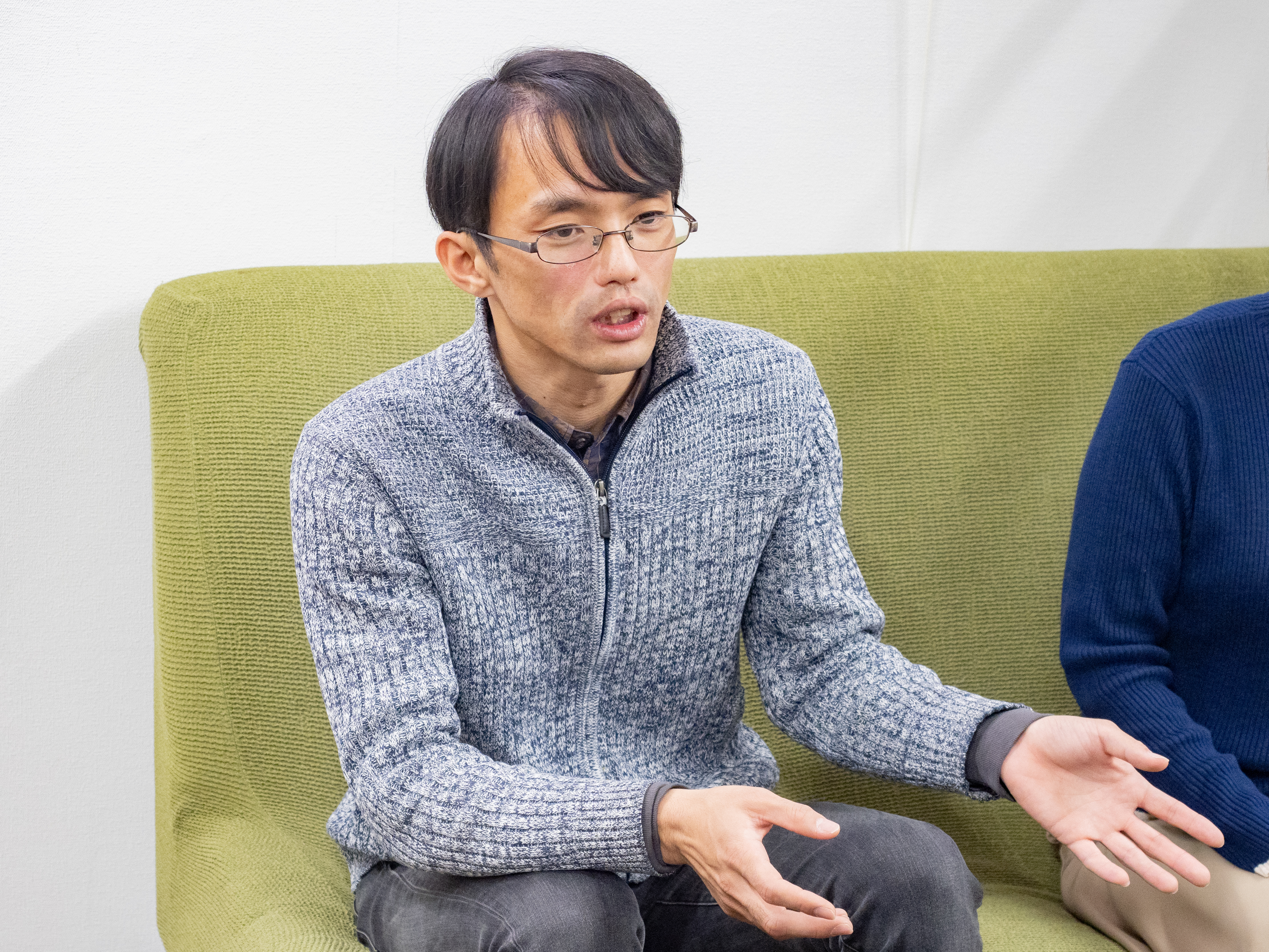
居場所づくりからさまざまな形の若者支援事業へ拡大
転機が訪れたのは2015年だそうです。「フリースペースは最初は私の自己負担で運営していました。2013年10月から1年限りの助成金を受けましたが、その後は資金が足りず継続が厳しくなりました。活動自体は順調だったのですが、いったんフリースペースは閉めることになりました」
フリースペース閉鎖後、中村さんは厚生労働省の就労支援事業に企画を応募し、採択されます。2015年に厚労省の委託として地域若者サポートステーション事業「ふくやま地域若者サポートステーション」を開設しました。フリースペース運営時、就労支援の必要性を感じたのが理由です。
翌2016年には広島県の委託事業として、退所児童等アフターケア事業に応募。採択され、カモ
ミールを開設します。
どりぃむスイッチの理事でカモミールの所長を務める粟木原 薫(あわきはら かおる)さんは「カモミールは児童養護施設を出た方や、虐待を受けた経験のある方などの、生活や就職の支援をしています。就労支援事業だけでなく、児童養護施設を出た方に対しての支援も私たちが取り組めるものなんじゃないかと考えました」と話します。
さらに2020年にはどりぃむスイッチの自主事業として、親を頼れない若者のためのシェアハウス「ピアホーム」も開始。2022年にはピアホームを、自立援助ホーム「エクリュ」に改めました。シェアハウスではスタッフとの対話が足りないと感じ、もっとスタッフと対話ができて密な関係が築ける施設にするのがリニューアルの理由だそうです。

支援が必要な若者の存在、安心できるこどもの成長環境の重要性 を多くの人に知ってほしい
2012年から社会参加に困難を抱える若者の支援活動をしてきたどりぃむスイッチ。長年の取組の中で、課題も感じているといいます。「まだまだ支援が必要な若者の存在が知られていないなと感じます。そしてこどもが育つときの環境には、何が必要なのかということもあまり気にされていないのです」と中村さん。
粟木原さん「取組を続けてきて、小さなころの環境が人生に大きな影響を与えると感じています。だから安心できる環境を与えてあげることは、非常に重要なことなのです。このことを多くの人に知ってもらいたいと思っています」
こどもが育つためのさまざまな要素のバランスがちょっとしたことで崩れて、つまずいてしまうことがあるそうです。それが不登校や引きこもりとして表れるのだと粟木原さんは言います。「それは親の育て方が悪かったからだとか思われてたりするのですが、決して親の育て方だけが問題というわけではありません」

若者が元気になることで福山が住みやすく豊かな街に
中村さんはこれまでの取組を振り返って「長く取組をしてきて、知り合いや関係者が増えてきました。顔が見える関係性が増えたのは、一つの成果だと感じています。つながりを生かすことで、可能性が広がっていくかもしれません」と語ります。
そして「何か社会のために役に立つことをしたいな」と感じている人と、困りごとがある人をマッチングさせるシステムがあればいいと語ります。たとえば車の運転が得意な人と買い物に困っている高齢者のマッチング。マッチングシステムがきっかけで、引きこもりの方が外に出るきっかけになる可能性があるといいます。
粟木原さんも言います。「福山市がもっと住みやすく豊かな街になるには、こどもや若者が元気でないとだめだと思います。だから次世代への投資っていうのは、みんなで取り組んでいくべきだし、そうする価値のあるものではないでしょうか。私たちの活動はその一環だと考えています」
また中村さんは「企業が社会に対する取り組みを積極的にしていることは、企業への関心や愛着につながり、人手不足や若手不足の解決のヒントになるのではないでしょうか」と話しました。
RECOMMEND
おすすめのSDGs
プロジェクトストーリー
一覧へ戻る